2、財務面から見た海外経営、リスク管理その後、ソニーに移り、経理・税務を4年間担当した。後半はCIOとして情報システムも担当。ソニーでは、二つの点で貢献できたと思う。一つは決算日程の短縮であり、もう一つは国際税務部門のニューヨーク移転である。 ●決算の正確さと決算日程の短縮 2000年までにはかなり詰めてきていた。5日かかっていた連結決算は連結ソフト・ハイペリオンを入れて一括で行えるようになり1日になった。現場は12日を4日にまで詰めていた。この4日をどうやって1日にするか。これが、2000年に私がソニーに移ってからのテーマだった。もちろん〆日を早めるといったまやかしはなく、正確性は担保した上での話である。 2000年の時点で機械化やIT投資は終わっていた。残るはBPR(事務プロセス改善)だけだったと思う。会計システムはITとの折り合いが割合ついていたが、最後まで残ったのは上海の合弁会社だった。どうやって1カ月遅れの決算から1日でやらせるか、これはとても大変だった。上海にソニーは2つ工場があった。更に蘇州、無錫に新しい工場ができていた。新しい工場は、システムも新しいものを使うし、日本で行っているとおりにやればいいのだから問題はない。しかし、合弁会社というのは結構大変だ。何回も足を運び、機械を入れ、システムを業務に合わせてカスタマイズすることなく、システムに合わせて仕事をしてもらうよう交渉を重ねた。最初、中国側から大きな抵抗を受けた。「なぜ、そんなことをする必要があるのか」と。私はとことん話し合った。時間はかかったが、やってくれた。こうして、まやかしなしの決算日程の短縮が可能となった。このとき私は、上海であれどこであれ徹底的に「話せばわかるのだ」と思った。 ●“ソニー通貨"の議論ソニーでは、いろいろなことに頭を悩ませた。例えば、資本コストの賦課をどうするか、全世界一律の資本コストの金利でいいのかどうか。あるいは為替リスクの問題に頭を悩ませ、今でも頭を悩ませ続けている。これは解がない世界かもしれない。 為替リスクは決算通貨の問題でもある。当時、「ソニー通貨」という話があった。ソニーコンピュータサイエンス研究所の高安秀樹先生が、「ソニー通貨をつくれば、為替リスクはなくなるのではないか」という議論を始めた。当時、私は高い視野からものが見られなかったのかもしれないが、困ってしまった。しかし今、これほど電子通貨が発達してくると、ひょっとすると、この先、次の世代のCFOの人たちは、自社内の為替レートを設定できるようになるかもしれない。あるいは自社内の通貨をつくれるかもしれないという感じがしてきている。最近、富士火災に社外役員に来ていただいた早稲田大学の岩村充先生が、『貨幣の経済学』という本を出されている。この本の最終章で、電子マネーの話をされている。もう少し先の話になるかもしれないが、為替リスクのヘッジも含めて、社内通貨は考えてもいいのかなと、このごろ思うようになった。 ●資源の最適配分と為替リスク資本コストの賦課金利を決定するとき、さまざまな国で事業を展開しているときどのような資本コストをベースに考えればよいのだろうか。 現地銀行をつくった場合、あるいは現地に資本を投入した場合どうするか。これは悩ましい。本来は、外国通貨で起債ができるわけだから、長期の債券を出してしまって、それに見合ってそのコストを付加すればいいのではないかと私は思う。そうすると、ライアビリティー(負債)と資本と相殺される。ただし、これはまた会計上の問題が出てくるが、そういう調達とのマッチングがあり得る話だと思う。銀行は、本来そうすべきだと私は思っていた。 メーカーについては、これは悩ましい。というのは、通貨を国別に行うと、シンガポールあり、マレーシアあり、タイありで、さらに通貨は飛んだり跳ねたりもする。しかも長期金利がないところがたくさんあり、為替のヘッジもできない。これを、そうするかという場合、結局資本コストはどんぶり勘定になっていると思う。国別に設定したわけではなくて全体でやっていた。ただし、これにも理由がないわけではない。東京から技術が行って、部品がいろんなところから来て、マレーシアで組み立てて、ヨーロッパへ行く。こうした場合、資本コストよりも通貨ヘッジに関心が向いてしまう。通貨ヘッジをうまくやったか否かで全く異なってくる。それでソニー通貨のような発想が出てくるわけだ。これについては、私はダメだと言い続けて、個別にヘッジしてきたが、まだ結論が出ない問題である。 AIGの場合は、すべてドルベースで見ている。ドルベースで資本コストを賦課してくるわけだが、これはもう全く通貨は関係なしで、ドルベースの資本コストで比べる。私は「これはおかしいじゃないか」と、反論してきた。日本のリスク・フリー・レートは10年で1%だ。米国は最近下がってきているが、大体4%で、3%差がある。3%差があるところへ、一律自己資本利益率の目標を8%から10%というのはおかしいのではないか、3%ぐらいまけてくれ、という議論を行う。サイズが大きくなると、そうなってしまう。それも、また一理あるのだ、結局、それがAIGの連結バランスシートにとってどう影響するかという話になるから、資本勘定のところ、出資勘定のところは、AIGの連結ベースでは、調達と合っている分、もう構わないという話になってしまう。「付加価値がどれだけ出るかという話だから構わない」という議論をされると、今、はやりのエコノミック・キャピタルモデルということになる。資本に対して、どれだけリスクをとっているかを相対的に見てくるから、個別の資本の付加コストよりは、付加価値に目が行く。私の議論もずっと通用しないため、そういうものかなとも思ってみるが、やはり現場ではおかしいという話になる。例えば、銀行にいたとき、ブラジルの人たちがものすごく儲かっているようなことを言う。現地通貨ベースで、である。しかし、ドルベースでは全く儲からない。これでは、ダメなのだ。やはり現地通貨ベースのことを忘れさせる必要がある。ということは、すべてドル会計、あるいは円会計にしてみると公平なのかなという気もする。今、私に解はない。 ●会計上のリスク会計上のリスクで言えば、ソニーはUS-GAAP(米国会計基準)で報告している。国際会計基準による報告も近く出ると思うが、最大の問題は、ソニー・フィナンシャル・ホールディングスという金融会社を持っていることにある。ソニー・フィナンシャル・ホールディングスは、日本の金融機関規制の問題もあって、日本会計基準で有価証券報告を行っている。せっかく、一生懸命決算日程を短縮して、US-GAAP上は、恐らく4月の第2週か3週には監査済みのUS-GAAPの報告書ができていても、日本基準の保険会社の決算は、5月の終わりにならなければ出てこない。このため、全体のUS-GAAPでの連結決算も5月終わりになってしまう。 これはかなりおかしな話だと思うが、東証は今後、US-GAAPを認めず、国際会計基準へ移行するが、ソニーにとっては今後も大変だと思う。ソニー・フィナンシャル・ホールディングスは、生保、損保、銀行がある。何とか早く、国際会計基準で、日本の銀行、金融機関の連結を国際会計基準で出して、ソニーの連結で合わせて出していくことになれば、スピードはまた早くなろうが、当分の間、彼らは後発事象のリスクを負わなければならなくなる。 富士火災も、2010年3月末に第三者割当増資を実施し、AIG系の損害保険持ち株会社チャーティスの連結子会社となった。6月末の決算から、US-GAAP(米国会計基準)での決算をやらなければならない。そのための体制づくりが大変だ。 ●税務リスク住友銀行時代、私は国際税務を行ってきた。銀行ではタックスの絡んだ取引、例えば、ブラジルのタックス・ペアリングなどを使った取引などを随分行っていた。ソニーに移ってからは、税務は大変だった。ソニーは世界80カ国ほどで取引をしており、しかもトランスファープライス(移転価格税制)をめぐる問題は年中行事のようになっていた。そこで、私は思い切って、インターナショナル・タックス・デパートメント(国際税務部)をニューヨークに移した。 これが、私の2番目のソニーに対する貢献である。アメリカに国際税務部門の女性のヘッドがいて、このヘッドが全世界を見ている。移転先の候補は、インターナショナル・タックスのスペシャリストが多い、ニューヨークかオランダだった。ニューヨークでよい人材を得て、スタッフとして日本人を送る。私が辞した後もこのやり方は続いているので、定着しているのだと思う。 富士火災はチャーティスの傘下に入ったので、税務は国内に限られる。国際税務についてはAIGの税務は、本当によくできた担当者がいるので大丈夫だが、国内では問題山積である。一つには消費税の問題である。保険会社にとって消費税アップは大きな問題なのだ。消費税が10%に上がると、我々のような小さな会社は大変だ。なぜなら、保険は消費税免税のため、後から事務費として消費税を付加して保険料を上げていくしかないからだ。5%から10%に上がった分を、何年かけて回収できるかという問題がある。その間の負担が大変なのだ。 もうひとつは法人税の引き下げがあると、国税当局は課税範囲を広げてくる可能性が高い。課税ベースを広げられて、一番弱いのは、これもまた保険会社である。事業会社と保険会社の両方を持つソニーで驚いたのは、保険会社は税務面で非常に優遇されていることだった。長期保険の獲得経費は設備投資即時償却のような話になっている。初年度にかかった獲得費用、契約費用として、いきなり落とせるのだ。ソニー生命はどんどん伸びていったが、国内基準では課税所得はそれほど出ない。こうした面が、法人税引き下げで見直される可能性があるのではないか。 この二つの税務問題が、保険会社にとっては大きな課題となってくる。 日本には、税務の専門家が少ないという問題もある。アメリカには、税務の弁護士がいるが、日本には税務の弁護士がおらず、税務問題で裁判所にはなかなか行かない体制になっている。国際税務、あるいは税務部門は、やはりアメリカのCFOと日本のCFOでは、関心の持ち方のレベルが大きく異なると思う。 税務は日本では、今まで国税との協調体制でやってきた歴史があるから人材があまり育っていない。私はアメリカにいたので税務については分かっているつもりだった。しかし、ペプシコから来たアメリカの女性ヘッドのほうが、私よりも余程よく分かっている。銀行サイドから見ていた税務とは、全くレベルが違うのだ。 ●ポリティカルリスクポリティカルリスクについては、私はソニーで大きな失敗を経験した。2000年、2001年、アルゼンチンで破たんが起こったとき、80億円ぐらい損をしたと記憶している(これは公表事実)。保険がかかっていなかったのだ。保険がかかっていないことを、本社が管理できないのが、ソニーのウィークネスだったと思う。やはりヘッジすべきものはすべてヘッジすべきだということで、ソニーではずいぶん頭を悩ませた。 AIGへ来て、フィリップスというソニーのヨーロッパでの競争相手のチーフ・リスクマネジメント・オフィサーの講演を聞いたとき、私は目からうろこが落ちたような気がした。彼は全部の保険、全世界で買っている保険を一元管理している、と言う。なぜ可能になるかと言うと、彼はすべての保険を有無を言わさず、自分のキャプティブ・インシュランス・カンパニー(100%子会社の再保険会社)に入れてしまう。すると、どういうリスクがあるか、何がどのくらいカバーされているかが全部分かるのだ。キャプティブに全部突っ込むことでリスクを把握するというのが彼ら流のやり方である。 ソニーもキャプティブを持っているから、保険をすべてそこに集中していれば、大体幾ら払っているかも分かるし、へこみや出っ張りがあるのも把握できた。 やはりヘッジすべきものはヘッジすべきだし、保険の購入は一元化すべきだと思う。日本企業の現状を言えば、多くの企業で、例えば役員賠償保険は秘書室が買っていたり、海外の労災は人事部が買っていたり、プロパティーは管財・総務部門が買っていたり、海上保険は運輸部門が買ったりする。どこでどんな保険を買っているかよくわからない。これは一元管理すべきだと思う。
協賛
|

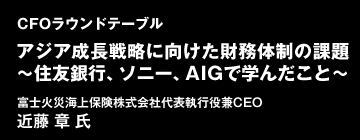

 1995年当時も今も、ソニーの連結決算は大変だ。実働の子会社が500程度あり、SPCも含めると1,000以上の会社を連結しなければならなかった。月次連結決算は、子会社(現場)での決算作業に12日かかり、データの収集と確認を3日で行った後、連結決算を出すのにさらに5日を要していた。総計20日間かかっていたわけだ。期末ともなると、もっと時間がかかり、決算発表は連休の後だったと思う。
1995年当時も今も、ソニーの連結決算は大変だ。実働の子会社が500程度あり、SPCも含めると1,000以上の会社を連結しなければならなかった。月次連結決算は、子会社(現場)での決算作業に12日かかり、データの収集と確認を3日で行った後、連結決算を出すのにさらに5日を要していた。総計20日間かかっていたわけだ。期末ともなると、もっと時間がかかり、決算発表は連休の後だったと思う。